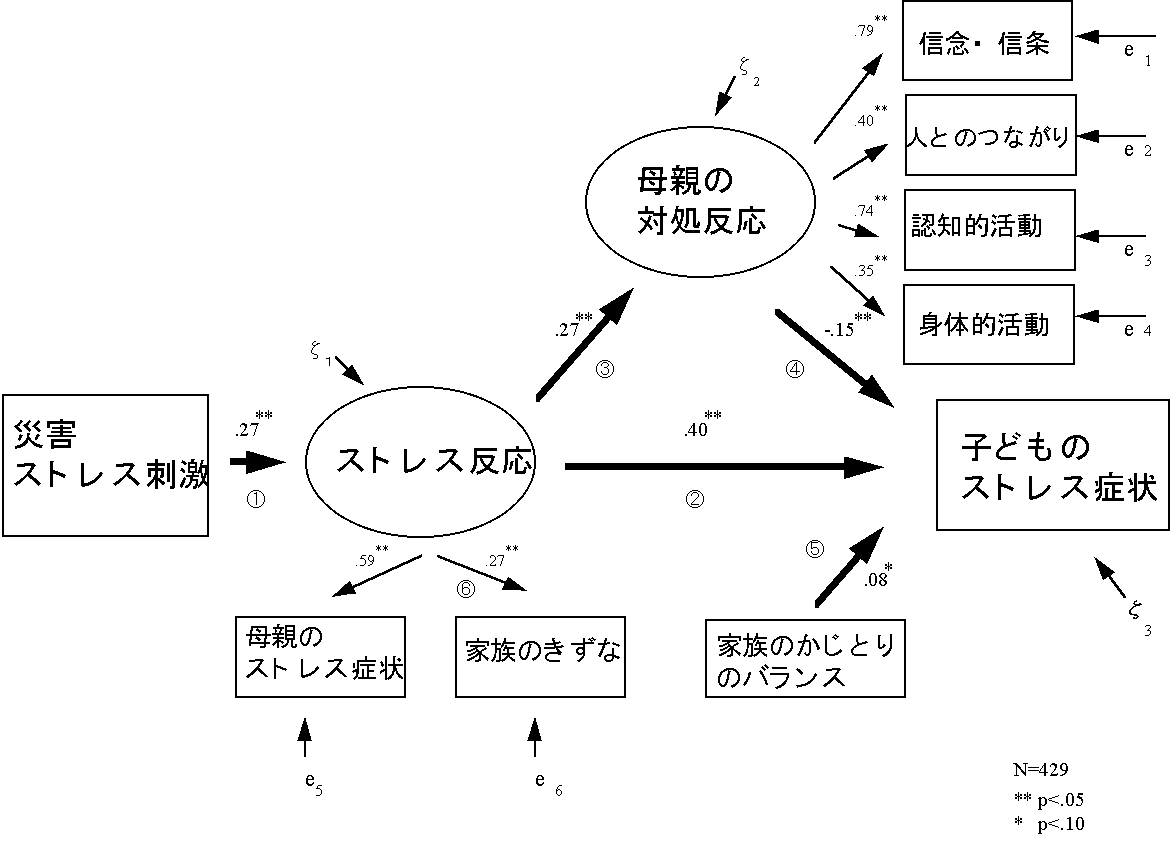
「災害ストレス・ケア活動の中の家族支援」
『喪失と家族のきずな』所収、金剛出版、1998年5月出版Ⅰ 震災体験背負い込み一人いやされぬ日々
震災からおよそ1年が過ぎたころ、神戸市内の幼稚園で、園児の母親の中川泰代さん(仮名)に聞いた話である。中川さん一家は同市東灘区に住んでいて、あのとき、5歳の長女と3歳の長男にはさまれ、川の字になって眠っていた。
「午前5時46分。ものすごいたて揺れで目が覚め、とっさに、3歳の長男を引き寄せようとしました。けれど、縦揺れで激しく身体が飛ばされてつかまえることができませんでした。やっとのことで、反対側に寝ていた長女を抱きしめました」
暗やみの中、中川さんは大声で長男の名前を叫び続けた。このとき、長男は倒れてきたタンスの下敷きになっており、夫がすぐに駆けつけてタンスを持ち上げて救い出したが、息が止まったいたそうである。幸い、息を吹き返し、目を開けたのだが、このこと以来、中川さんは「長男に申し訳ない、救ってあげられなかった」という罪の意識に苦しんできた。
夫や実家の両親などにも、それとなく自分の気持ちを打ち明けようとしたのだが、「ともかく生きていられただけでも幸せだった」、「そんな甘えた気持ちでどうする」、「母親なんだからもっとしっかりしなくては」などと励まされるばかりだった、と語ってくれた。
これは神戸市児童相談所のソーシャルワーカー、児童精神科医、心理判定員と一緒に、市内の幼稚園へ巡回相談にいったときのことである。巡回相談では、母親たちにグループになってもらって震災の体験を聞き取った。それも普段は押さえている感情のレベルにまで立ち入って話してもらった。何人かの母親が、じっと中川さんの話に聞き入り、「わたしも同じようなことを言われたのよ」とつぶやいた。
私は「これほど申し訳ないと悩んで下さるお母様を持てた坊ちゃんは幸せですね」と言った。「あなたが悩んでいらっしゃるのは、あなたが本当に良いお母様だからなのですね」と...
その言葉に、今まで押さえていたものが一気にあふれ出たのか、中川さんは実に気持ち良さそうに涙を流した。そして「自分はずっと気持ちを張りつめて生きてきました。けれども、やっぱり色々とストレスがたまっていたのですね。自分の気持ちをしゃべることで、すごく気分が楽になりました」と言って帰っていった。
Ⅱストレス発散しにくい立場
私たち神戸市児童相談所のチームは1995年暮れから翌96年の春にかけて、神戸市東灘区や灘区、長田区などの20の幼稚園で巡回講座を開き、相談を行った
4)。巡回講座では、最初に30分ほどストレスとその対処について講演をおこなった。その際、てんびんをたとえに使った。てんびんの片方にはストレスをもたらす刺激(ストレッサー)がのる。もう片方は、それを和らげるための資源である。このふたつのバランスが取れていると感じられると、ストレスに対処することができる
6)。神戸の母親たちは、震災により非日常的なストレッサーにさらされた。さらに震災後の生活も混乱にあふれたものだった。このような状況で、てんびんが大きくストレッサー方向に傾かないようにするには、ストレッサーを減らす(例えば被災地外への疎開など)か、対処資源を増やす(対処能力のエンパワーメント)かである。逆に言えば、幼児や母親を包み込む家族システム全体の資源性や母親の心理社会的対処資源をエンパワーすることにより、てんびんのバランスを積極的に保つことができる。
小講演が終わると、母親たちを7~8名のグループに分け、それぞれの体験にじっくり耳を傾けた。そして押さえていた感情を安全に表に出してもらうようにした。実は私たちはもともと、「子どものケアにとって母親の役割がとても大切です」といったことを話して回るつもりでいた。ところが、実際に幼稚園で話を聞くにつれ、疲れているのは子どもたちよりもむしろ母親の方なのだと実感するようになった。
巡回相談と併せて行った震災ストレスの調査でも、このことは明らかになった。この調査では、1.実際の震災被害の程度、2.母子の心的外傷後ストレス症状の程度、3.家族システムの資源性、4.母親個人の心理社会的対処資源と、5.それぞれの要因間の因果関係について調べた。その結果、438組の被災母子の調査から見えてきたのは、「大半の幼児は母親によって災害の影響から守られていた」が、「幼児を抱える母親は自分自身のストレス発散の場や機会が少ない」というものであった
11)8)13)。1.震災による被害
震災による自宅の被害では、まったく影響がなかったと答えたのは438組の母子のうち約1割に過ぎなかった。一部損壊が約6割、半壊が約2割、全壊が約1割という被害の程度であった。震災直後の対応では、半数はそのまま家にいたが、残りの半数はすぐに家族と避難していた。避難していた期間は、9日以内が約5割と一番多かったが、1ヶ月以内約1割、2ヶ月以内約2割、それ以上の期間避難していたものも約1割いた。またライフラインについては、電話・電気などは大半が2~3日で復旧していた。しかし水道では約半数が2ヶ月近く断水していた。さらに都市ガスにいたっては、約半数が50日以上不通だったと答えている。
母親たちの生活は、震災そのもののショックに加えて、その後のライフラインの切断により、日常生活がおよそ3カ月近くにわたって混乱したことを示している。それが、さまざまな苛立ちごとにいろどられた毎日であったことは疑う余地もない。
2.心的外傷後ストレス症状
調査の中で、幼児のストレスの症状は米国の精神科の診断基準(DSM-IV)をもとに、神戸市児童相談所が独自に作成した質問紙を用いた。全体で21項目のストレス症状について訊ねているが、「たびたび」や「いつも」あると答えた項目には、「5.親と一緒でなかったり、明かりがついていないと寝床に入れない」(30.5%)、「家族や友人と一緒でないと不安そう」(21.4%)などの不安症状が目立った。それ以外には、「21.他の子どもの世話をしようとすることがある」(23.4%)といった過剰適応や、「15.ひどく甘えて、わがままを言うことがある」(13.7%)といった退行(幼児返り)」症状が目についた。しかし、診断項目の多数にわたって「ある」と答えた重症なストレス症状の子どもは全体の2.5%(11名)と、比較的少数だった。
一方で、母親自身に「最近1週間であてはまること」を聞いたところ、「14.地震に関係するものを見ると、どんなものでもあの時の感覚がよみがえった」(29.7%)、「1.そのつもりがないのに、地震の起こった瞬間を思い出すことがあった」(19.8%)、「5.震災について考えると何度も強く感情の波がおしよせた」(18.4%)など再体験(フラッシュバック)反応が上位を占めた。この質問項目は、Horowitz, M.らの
Impact of Event Scale 3)の15項目を日本語に訳したものである。この尺度は、災害によるストレスが引き起こす再体験と否認という二つの反応の程度を測る。ストレス症状が重症な(いくつもの項目にハイと答えた)人は全体の8.2%(36名)で、子どもの場合よりも3倍の高率だった。これらの母親はPTSD(心的外傷後ストレス障害)が強く疑われたのである。3.家族システムの資源性(きずな・かじとり)
Olson, D.H.の円環モデルは、家族システムの資源性を「きずな」と「かじとり」という二つの次元からとらえる。「きずな」とは家族成員が互いに対して抱く情緒的なつながりのことである。「かじとり」とは状況的あるいは発達的なストレスに対して、夫婦・家族システムの権力構造や役割関係・ルールなどを変化させる能力のことである。きずな・かじとりとも、極端に高過ぎても、低過ぎてもシステムとして機能しない。ちょうどその中間の状態にあるときに、家族機能は最大限に発揮されるというのが円環モデルの考えかたである。従って、資源性を高めるにはきずな・かじとりとも中庸な方向に近づけることが指針となる。
巡回相談とあわせておこなった母子のストレス調査では、家族のきずな・かじとりの様子をさぐるために、関西学院版家族システム評価尺度第3版(FACESKGⅢ)を用いた。これは、円環モデルにもとづきながら、実際の質問項目はすべて日本の家族に当てはまるようにオリジナルに作成したものである。第3版からは、家族のきずな・かじとりと家族資源性の間のカーブリニア関係(各次元の両端は家族システムの低機能と関連し、中程度の時にシステムの機能が最適となる関係)をより忠実に反映させるためにサーストン尺度を使っている
14)。4.母親の心理社会的対処資源
イスラエルのLahad, M.らのグループはストレスを和らげる対処スタイルを6つに大きく分類した。その頭文字をとって、BASIC-Phモデルと名付けた
5) 。BはBeliefで信念・信条の力、AはAffectで感情の力、SはSocialで人と人とのつながりが持つ力、IはImaginationで空想や想像がもつ力、CはCognitionで情報収集や問題解決などの現実吟味の力、PhはPhysicalで身体的活動力である。人はストレスを感じたときに、それぞれ自分が得意とする対処スタイルの力を動員(エンパワー)して安定を図るのだという。私たちの調査用紙には、震災後の混乱に母親たちがどのように対処したのか自由に記述する欄を設けていた。そこには、日常の生活が混乱するなかで、「人とのつながり」、「情報収集などの認知的活動」といった対処資源を活用して、生活の知恵を生かした母親の賢さ、強さが如実に現れていた。ある母親は今回の震災を振り返って「子供は母親が守る!今回は私一人で守ったぞ!!と自信を持つ事位でしょうか、今回の地震で得たことは」と書いている。まさに災害は、ソーシャルサポートや現実吟味、積極的な活動といったパーソナル・エンパワーメントを母親たちにもたらしていた。
表1:BASIC-Phモデル挿入
5.震災ストレス対処の因果モデル
神戸の母親たちは、震災がもたらした混乱や緊張(ストレッサー)に対処しようと、自分が得意とする対処資源を活用してストレスを発散させていた。けれども、構造方程式モデルを用いたストレッサー(震災被害)、母子のストレス反応(PTSD症状)、家族システム資源性(家族のきずな・かじとり)、心理社会的対処資源(BASIC-Ph)、などの要因間の因果関係について分析すると、①「震災による生活困難は母親に直接ストレス反応を引き起こし」(図1の矢印①参照)、②「その反応の結果として子どもにストレス反応が生じた」(矢印②参照)が、その一方で③「この困難な状況に積極的に対処するため母親はストレス対処策をエンパワーして資源性を高め」(矢印③参照)、④「それによって子どものストレス症状を緩和していた」(矢印④参照)ことが明らかになった。さらに家族システムの資源性因子に注目するなら、⑤「家族内の役割やきまり、力関係などの柔軟さ(家族のかじとりのバランス)は、子どものストレス低減と結びついていた」(矢印⑤参照)が、⑥「家族成員間の心理的・社会的距離(家族のきずな)は、ストレッサーに対する反応として自然と高まったが、それは表面的な現象にしか過ぎず、ストレス緩和にはあまり関係していない」(矢印⑥参照)ことも示唆された。
図1:因果モデル挿入
調査から明らかになったのは、母親の努力は子どものストレス症状の緩和にそそぎ込まれていて、母親自身のためにはいっさい使われていない、というものだった。家族システムのレベルでの対処資源も子どもの症状緩和には関係しても、母親のストレス症状緩和には役立っていなかった。母親のストレス症状を和らげる資源はどこにも見あたらなかったのである。
Ⅲ災害ストレス支援の原則
私たちの調査は巡回相談での印象を実証的に裏付けるものだった。母親たちの体験にじっくりと耳を傾け、状況や症状の肯定的な再評価を促す一方で、「子どもに注ぎ込んでいた対処資源を母親自身のために用いてもかまわない」と保証すること。それが、母親たちをエンパワーする。このような概念図式にそって巡回相談を続けた。その結果として私たちなりの心理教育モデルができあがっていった。最後に、その概要について、1.援助のエコロジー、2.症状のノーマライゼーション、3.協働とエンパワーメント、4.被災体験の意味付けという4つの視点からまとめることにする。
1.援助のエコロジー
巡回相談を始めるにあたって私たちには一つの直感があった。大半の被災者はメンタル・ケアの専門家には近づかないだろう、というものである。なにより私たち自身が被災者であり、「自分なら見ず知らずの専門家に悩みなどを語るまい」と素朴に感じていたからである。被災者へのメンタル・ケアは必要だが、通常の臨床モデルにもとづく心理臨床的な関わりには強い拒否感がある。それが、被災者への支援が置かれた文脈(援助のエコロジー)
12)だった。震災から約1年がたった頃、日本赤十字社を通じて林春男らのグループが、被災自治体10市10町で行った大規模サンプリング調査
2)もわれわれの実感を実証的に裏づけている。林らの調査によれば、震災後大半の住民が「こころの悩み」を感じたが、それを精神科医やカウンセラーといった専門家に相談したのは、極めて少数だった。むしろ大多数の被災者は、家族や知人・友人などの非専門的な支援者から必要な心理的サポートを得ていたのである。面接室で相談に訪れる人を待つのではなく、こちらから出かけてゆくこと(アウトリーチ)がなにより大切だった。その際、「こころに悩みをもち人に助けを求める」クライエント役を押しつける心理臨床モデルは不適切だった。
ところで、林らの調査によれば、専門援助者のなかで唯一例外的に活用されていた職種がある。地域のかかりつけの医師たちである
2)。なじみのドクターには、かなりの数の被災者がワン・ダウンの立場で、こころの悩みについて打ちあけていた。医療以外の枠組みで、悩みをうちあける相手として抵抗がさほど高くないと予想される領域がもう一つあった。それが教育である。そこで、神戸市児童相談所のアウトリーチ・チームが採用したのが「出張講座・勉強会」という枠組みであった。私たちは教師役として幼稚園を訪れ、災害ストレス反応やコーピングについて、30分程度の小講義をした。その後小グループに分かれるが、それはあくまで学習を補助する「勉強会」という体裁をとった。小グループでの体験の聞き取りも「押さえていた感情を安全な場で口に出すのは良いことだ」と保証し、そうすることがストレス発散につながると実感してもらうための手段と位置づけた。そしてグループの後半部分では、今後の見通しについて触れた。地震の瞬間が急にイメージとして浮かんだり(再体験)、あるいは逆に地震についてまったく何も考えたり感じたりしない(否認)時期が今後も交互に訪れるだろう。そのような両極の反応の間を行きつ戻りつしながら、やがてその振幅がせばまりながら回復へといたるのだと知らせた。そして、もし不安にさいなまれた時には、自分の中にある健康な部分、強い部分を活用してストレスに対処することができるのだと説いた。将来について見通しを持ち、対処策があるのだと心理教育を行うのがアウトリーチ・グループの一つの機能であった。
2.症状のノーマライゼーション
災害後のストレス症状により、多くの被災者が内心「自分は普通ではなくなった」という強い不安感をもっていた。全体への講義や小グループでの話し合いを通じて強調したのは、災害ストレス症状がいかに有用なものであるか、という点である
9)。たとえば次のような説明をした。
生命が脅かされるほどショッキングな事件に出くわしたとき、生物としてのヒトは、「闘うか、さもなくば逃走するか」といったもっとも原始的な反応を示します。たとえば、戦闘や大災害の最中に無防備に眠ってしまった種は生き延びることができなかったでしょう。つらい体験に無感覚になることは闘いを続けるために不可欠のことです。そして危機がひとまず通り過ぎたあとでは、災害の瞬間が頭の中で再現されるために、二度と同じ目に遭うまいという警戒心が持続します。このような反応のおかげで人類は現在まで種を保存することができたのです。
災害ストレス反応が、現に今、ここで生じている事実こそ、一番原始的なレベルで命を守ろうとする機能が働いている証拠だった。このようにして症状をノーマライズしたあとで、決まって以下のような言葉を贈って会を終えていた。
あなたがつらくなっているのは、あなたに力がないからではありません。むしろあなたがとても良い母親だから、お子さんのためにすべてを使ってきたからなのです。お子さんは前と比べてだいぶ安心できるようになりました。本当によくがんばられましたね。でも、これからはその力を自分のためにも使ってあげていいのですよ。
被害者・被災者としの無力感や罪障感こそ、まさに母親としての役割を誠実に担ってきてからこそ生まれたものであり、それは「良い母親であるからこそ」の感情であるとリフレーミングを行った。このように体験を再評価することによって母親たちの対処能力を高める、というのが私たちの戦略だった。
3.協働とエンパワーメント
心的外傷からの回復の過程で被災者は、再体験・回避・覚醒亢進、罪悪感といった特有の反応を示すが、その最良の癒やし手は、被災者自らであり、さらには被災者と日常接する非専門的な支援者たちである。災害直後に求められるものは、セラピーといった高度に専門的な知識ではなく、日常の知恵に属するものである。日常の知恵や常識は一般の生活者によって広く共有され、地域の中に豊かに存在する対処資源である。
1995年6月、私たちのグループは国際ロータリー第2680地区災害復興委員会および米国ユダヤ人協会の支援を受けて、米国とイスラエルから心的外傷後ストレスの専門家を招いてシンポジウムと専門家向けのワークショップを開催した。その折り、米国から訪れたのがホロコースト生存者や広島の被爆者の心理学的研究で高名なニューヨーク市立大学教授Lifton, R.(ロバート・リフトン)博士であった。リフトン博士は災害直後の被災者への「心のケア」とは何か、を暗示するために一枚の漫画を描いた。それは2羽の鳥の会話で、1羽が「今日、私は心に傷を負った」と言う。それに応じて、もう1羽の鳥が「おむすびを食べなさい」と答えるものだった。災害直後のメンタルケアとは、カウンセリングでもなく、心理療法でもなく、まして投薬でもない。それは、白いおむすびであり、温かい炊き出しであり、毛布を差し出すという日常の知恵や常識である。リフトン博士の漫画はそう訴えていた。
リフトン博士の漫画を見て、すぐさま思い出したのは、震災の報を聞くやすぐさま雲仙・島原から駆けつけてきたボランティア協議会の人たちのことである。このグループは震災翌々日には、東灘区の公園に大きなテントを張り、近隣の住民を招いてカニすきの夕食会を催した。その際に車座になった一人一人が自分の体験を語っていった。島原のボランティアがしたことはまさに災害緊急時のストレス・ディブリーフィングそのものだった。しかも、一人一人への時間配分やステップの進行があまりにも機械的すぎ、場合によってはむしろ災害体験を悪化させると最近になって批判を浴びるようになってきたMitchell,J.T.流のCISD(
Critical Incident Stress Debriefing)7)と異なり、島原の人たちは、まず暖をとる場所と、湯気のたつ鍋物と、そしてじっくりと腰をすえて被災者の話しに耳を傾ける共感の態度を神戸に持ち込んでいた。そして、災害直後の反応が極めて正常なものであることを自らの体験を例にして語り、今後の見通しについて希望を与えていたのである。雲仙・島原ボランティア協議会の人たちが行った活動こそ、最も自然な援助のあり方だった。一方、専門家にできることは、症状を明確に既述し、説明し、癒やしへと至る時間の流れの中に現在を位置づけることである。両者はそれぞれの役割を自覚し、被災者自らの力を高め、尊厳や有能感を回復するエンパワーメントの視点から協働すること
10)が求められるのである。4.被災体験の意味付け
BASIC-Phモデルは、イスラエル・カルメル社会科学研究所所長のGal, R.(ルーベン・ガル)博士から直接ご教示いただいたものである。1995年6月のワークショップの講師として、ニューヨークのリフトン博士とともに、イスラエルから神戸に来たのがガル博士だった。
ところで、なぜイスラエルなのか。実は神戸とユダヤの人々とは深いつながりがあったのである。
第2次大戦の最中、リトアニア日本総領事館に杉原千畝という外交官がいた。杉原領事代理は、1万人近くのユダヤ人に日本への出国ビザを発給した。そのおかげでナチの虐殺から危うく逃れることができた。これらのユダヤ人難民が、日本で上陸した地が神戸だったのである。
当時の神戸市民は、これら新来の難民達を人道的な立場から手厚くもてなしたという。多くの市民が、衣類や食料を差し出したのである。神戸市の当局者は、難民の最終受け入れ国が決まるまでの間、彼らの滞在を認める決断をした。難民に手をさしのべた当時の神戸っ子は、彼らの行為が政府の方針に反することなのか、沿うことなのか、確たる思いのないまま、ただ「いてもたってもいられない」気持ちにつき動かされて、支援したのである。
恩義のある故杉原領事代理のために、そして神戸のために。ユダヤ系の人たちが音頭をとった神戸復興のための「スギハラ」基金に全米から義援金が寄せられた。そのおかげでイスラエルからガル博士を、そして米国からリフトン博士を招き、災害ストレスとその対処について学ぶことができたのである。
神戸でのシンポジウムで、リフトン博士は、災害被害者の希望について語った。被災者はどのようにしてもう一度自分の人生に向き直すのか。「被災体験には意味があったのだ」と感じられること、そのために活動を起こす時に、「被災者」であることを越えるのだ、と満員の聴衆に話しかけた。
アウシュビッツを生き延びた精神科医Frankl, V.も、生きることの意味について語っている。
私たちが人生に何を求めるのか。それは大した問題ではない。むしろ人生が私たちに何を求めているのか。それが問題なのです...生きるということが究極に意味するのは、人生が私たちに何を求めているのかについて正しい答えを見つけ、人生が私たち一人一人に対して絶えず課し続ける課題を果たす。そのことに責任を取るということなのです
ホロコーストを民族の記憶に刻印づけたユダヤ系の人々は、まさにその体験ゆえに、戦後50年にわたり、世界各地の災害被害者に対して普遍的な友愛と連帯の行動を起こしてきた。それは、「被災者である」という実存の危機に正面から立ち向かうことであった。
島原ボランティア協議会の人たちも、雲仙普賢岳の火砕流による被害者であった。しかし、被災体験が深化する中で、阪神淡路大震災の報を聞き、すぐさま行動を起こした。そして「被災者であること」を越える瞬間を体験したはずである。
被災者であることを越える。そのためには、様々な機会や試練に自らをさらし「あの体験には意味があった」と信じることのできる瞬間が訪れるのを待たなければならない。
これが、母親たちを含めて阪神間に住む私たちが、震災から3年を迎える今、直面する課題なのである。
引用文献
表1:BASIC-Phストレス対処スタイルモデル(Lahad & Cohen, 1983)
|
|
信念 Belief |
情動 Affect |
つながり Social |
想像力 Imagination |
認知 Cognitive |
身体的活動 Physical |
|
理論基盤 |
フランクル マズロー |
フロイト ロジャース |
エリクソン アドラー |
ユング デ・ボノ |
ラザラス エリス |
パブロフ ワトソン |
|
鍵概念 |
信条 価値 信仰 正義 大義 意味 |
防衛機制 浄化 換気 表出 (言語・非言語)
|
役割 組織 仲間 所属
|
創造性 遊び 空想 好奇心 擬人化
|
情報探索 現実知覚 現実吟味 優先順位づけ 問題解決 ローカス・オブ・コントロール |
活動 運動 ゲーム リラクセーション |
|
示唆される 援助技法 |
論理療法 実存療法 |
受容 共感 |
社会的スキル アサーション ロールプレイ |
イメージ誘導 スクリブル ビブリオセラピー |
認知療法 |
行動療法 (オペラント条件づけ・系統的脱感作・フラッディング等) |
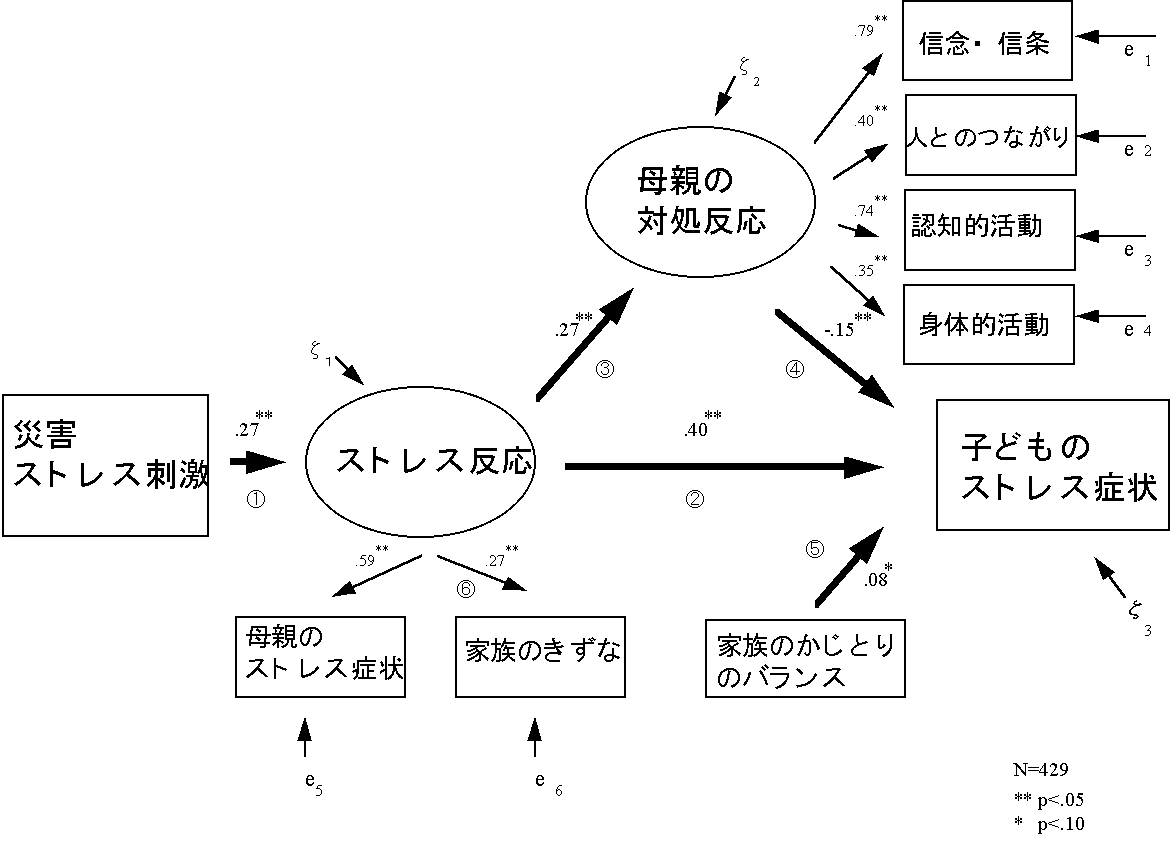
図1:災害ストレッサー・ストレス反応・家族資源性・個人の心理社会的資源性間の因果モデル分析の結果(GFI=.9700, AGFI=.9437,
適合度カイ自乗=62.6627, df=24, AIC=14.6627, HoelterのN=250)